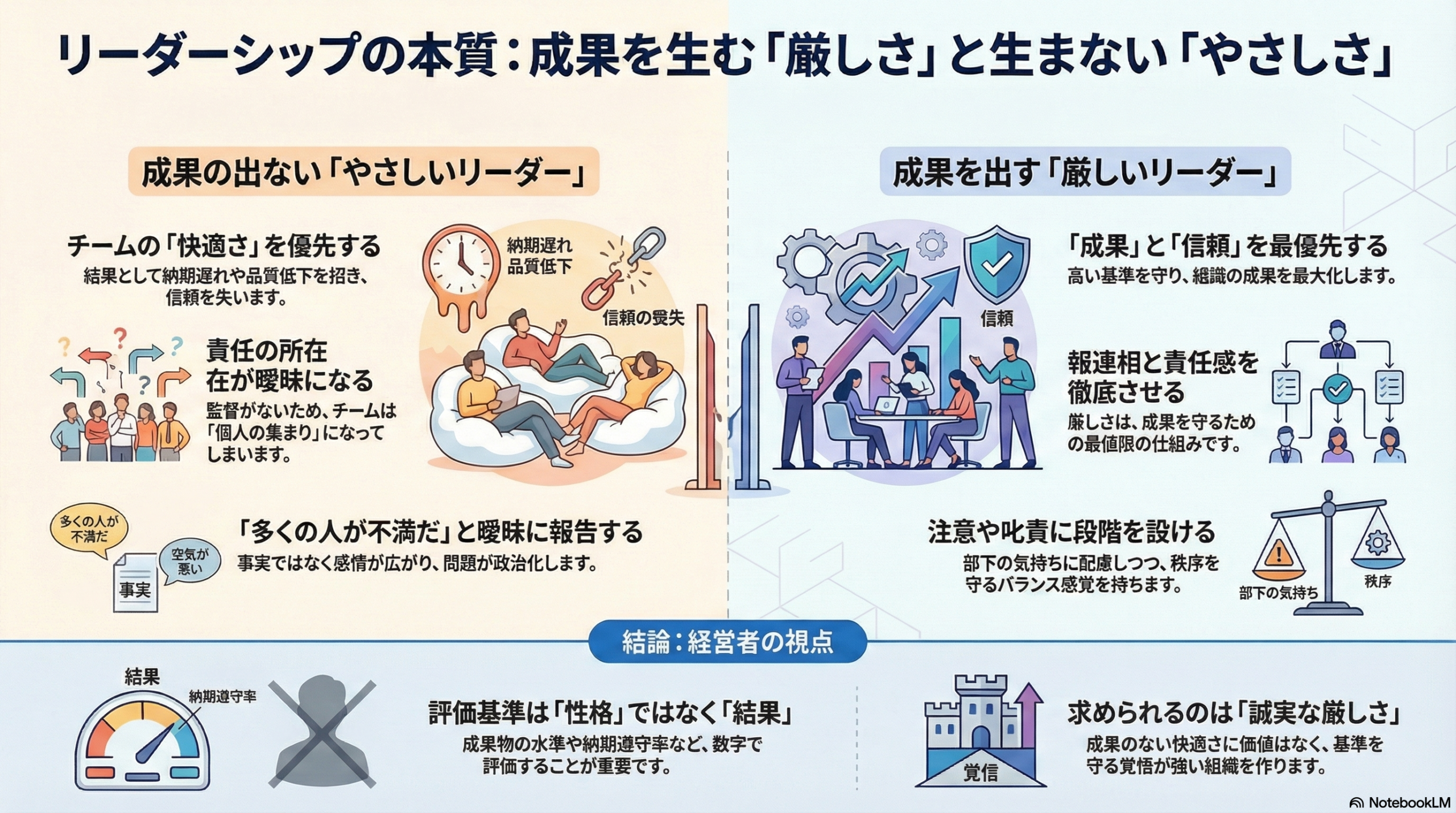リーダーの在り方について、社内で小さな波風が立つことがあります。
「厳しすぎる」「怖い」「話を聞いてくれない」──。
そんな声が出たとき、経営者としてどう向き合うべきか。私はいつも、感情ではなく「成果」と「責任感」という軸で考えています。
「many people are complaining」という言葉の危うさ
人事・総務の立場にある人が、
「多くの社員が不満を言っています」と報告してくることがあります。
しかしこの “many” という言葉ほど、組織を曇らせるものはありません。
人数も名前も曖昧なまま「みんながそう言っている」と伝えると、
実際には一人二人の感情が、あたかも組織全体の意見のように膨らんでしまう。
事実の共有ではなく、政治の匂いを帯び始めます。
私はこの「many」という言葉を、社内報告で使うことを禁止しています。
リーダーが厳しいのは悪いことではない
リーダーが部下に対し、「レスポンスが遅い」「連絡がない」と指摘する。
それは当然のことです。
特にリモートワークでは、監督がなければ責任の所在があいまいになります。
「監視されたくない」という気持ちは理解できますが、
監督がなければチームは組織ではなく“個人の集まり”に変わってしまう。
厳しさは、成果を守るための最低限の仕組みです。
「やさしいリーダー」が必ずしも良いチームを作るわけではない
中には、「もっと優しく」「笑顔で接してほしい」と願うメンバーもいます。
しかし、いつもニコニコして「OK, OK」と言うだけのリーダーが、
日本基準の成果物を作れるでしょうか?
私は過去に“やさしいだけのリーダー”を見てきました。
結果はどうだったか──納期は守られず、品質も下がり、責任の所在も曖昧。
ローカル基準であればそれでも通用するかもしれませんが、
日本の顧客に納めるレベルには到底届きませんでした。
チームの快適さよりも、成果と信頼こそがリーダーの仕事です。
「叱る」ことにも段階がある
今回、あるリーダーは私にこう言いました。
「まずは私から口頭で注意します。
あなたがレターを書くと重大に受け止められるので、
それでも改善しなければその時に書いてください。」
この発言に、私はリーダーとしての成熟を感じました。
単に厳しいだけではなく、「どの段階で、どの強さで伝えるか」を考えている。
部下の気持ちにも配慮しながら、秩序を守ろうとしている。
そのバランス感覚こそが、私が求める“強くてやさしいリーダー”の姿です。
経営者が見るのは「性格」ではなく「結果」
私はどちらの味方でもありません。
関心があるのは、ただ一つ──結果と責任感です。
リーダーが厳しくても、成果が出ているなら評価します。
優しくても、品質が落ちているなら評価できません。
リーダーの本当の価値は、部下からの人気ではなく、
成果物の水準・スケジュールの正確さ・報連相の密度で決まる。
数字にすれば一目瞭然です。
ある3人のリーダーを比較したとき、
成果・納期・報連相を総合して私はこう評価しました。
- Leader A:9
- Leader B:3
- Leader C:1
どのような結果を出すかが、すべてです。
社内コミュニケーションの原則
最後にもう一つ。
なぜ本人に直接言えば済むことを、総務を通して複雑にするのか。
同じ国の仲間同士、言葉は通じるはずです。
誤解や対立を恐れて遠回りをすると、問題はむしろ大きくなる。
会社とは「話を簡単にするための仕組み」です。
複雑にするのではなく、率直に、正面から話す。
これが一番の近道です。
結論
リーダーに求められるのは、「やさしさ」ではなく「誠実な厳しさ」です。
そして経営者に求められるのは、「人気」ではなく「基準を守る覚悟」です。
チームが気持ちよく働くことは大切。
しかし、成果のない快適さに価値はありません。
リーダーの厳しさを恐れず、正しい方向にチームを導いていく。
それが本当の“強い組織”だと私は思います。